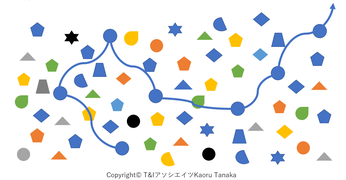T&Iアソシエイツの田中です。
「ChatGPTをうまく使えるのは誰か?」
そう問われたとき、多くの方は“デジタルネイティブな若者”を思い浮かべるかもしれません。けれど実際には、そう単純ではありません。
ある企業の70代の会長が、私の生成AI講演後に企業内研修を依頼してくださいました。
「自分にはITは無理。でも、会社の未来を思えば、社員には活用してほしい」とのことでした。20~70代の社員が参加した研修のあと、会長に車で送っていただいた際、私はこう申し上げました。
「若手の方がITに慣れているのは確かですが、“活用の目的”がなければ、使いこなすのは難しい。むしろ、日頃から問題意識を持ち続けているベテランの方こそ、食わず嫌いさえ克服すれば、生成AIを効果的に使えるはずです。」
会長は深くうなずき、それ以来ChatGPTを積極的に試すようになったそうです。
一方、米国の一流大学で2つの学位を持ち、数学や物理に精通した60代の知人(日本の大学院で研究中)は、なかなか生成AIの活用に踏み切れずにいました。私はメールでこう伝えました。
「浅い使い方でも、一定の回答は得られます。しかし、精度の高い情報を引き出すには、適切な指示や質問が必要です。適切な指示・質問をするには人間にそれなりの能力、一定の知識や推察・洞察・判断力が求められると思います。」
「人間の部下や先生に良い指示・質問ができる人はAIともうまく付き合えます。きっとあなたは研究の良き相棒として生成AIを活用できるはずです。」
加えて私は、研究における各種生成AIの活用の仕方や留意点を伝えました。
それをきっかけに彼はついに生成AIを研究に導入しました。
生成AIの活用には「ITスキル」よりも、問題を見つける力や自ら解決しようとする姿勢が求められます。つまり、「問題意識」と「当事者意識」が鍵です。
受け身な職場では、生成AIの活用は広がりません。
生成AIを味方につけ、組織の知的生産性を高めていくためには、次のような力が必要です。
- 問題意識と当事者意識:AIに「問い」を投げかける力
- 推察・洞察・判断力:AIの「答え」を見極める力
闇雲にリスキリング研修を実施しても、「何のために使うのか」が曖昧では活用は定着しません。
さらに、生成AIと“協働”するだけでなく、“共創”へと発展させていくには、一段深い視点と学びが不可欠です。
AIと協働・共創する人材育成に関心のある方へ
貴社の人材育成や生成AI導入の推進をワークショップ型研修や伴走支援でサポート致します。お気軽にご相談ください。